教員Voice 伊藤 博之先生インタビュー
日本の自発的学習の源流をさぐる
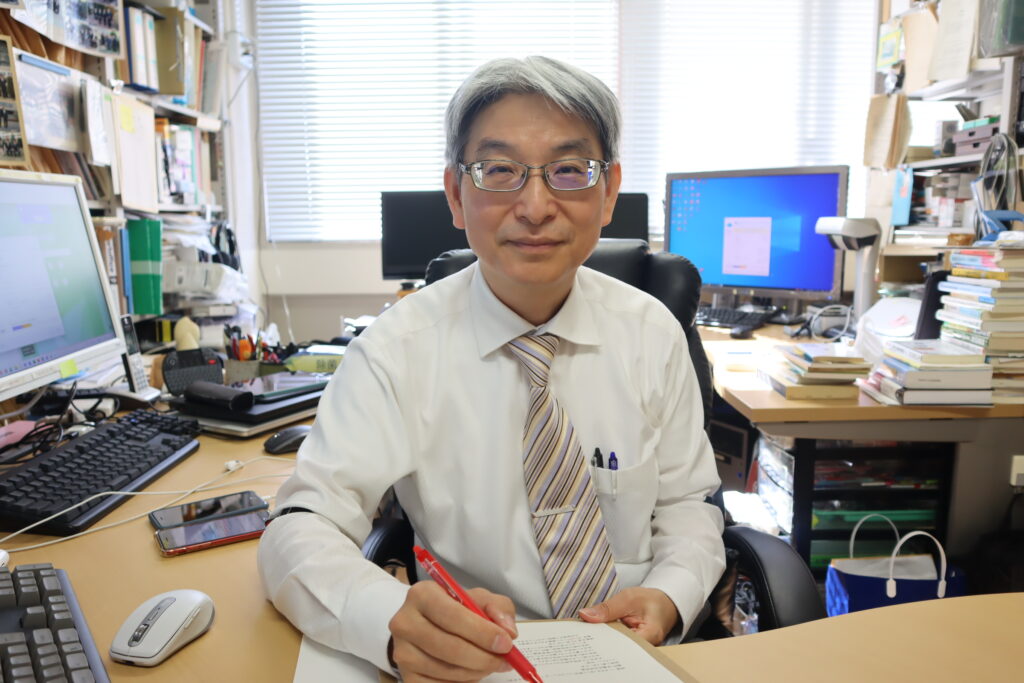
――学生生活を振り返って、改めて思い出される印象的な出来事はありますか?
授業には最低限出席するだけで、自分たちで勉強などを行っていました。私はシャイであまり外に出て行くのが得意ではないので、教育学部の中のサークルに、かなりの時間を費やしていました。記憶に残っているのは、僻地教育のサークルです。そこで授業を見たり、場合によっては自分たちで授業をさせてもらったり、地域の人たちとディスカッションとか、お酒飲みながらお話をしたりしたうえで、活動をまとめて報告書を書くということを年に4回程度行っていました。京都大学の場合は、そうしたサークルに大学院生も所属しているので、そこで縦の繋がりを得ていました。そういう人達と計画立てながら、時には後輩を指導したりすることを積み重ねてきました。あとは、基本的には本を読んでいました。大学での授業の中身なんて、せいぜい新書版一冊か二冊分です。それこそ授業を聞くより、自分たちで読んだ方が頭に入る。だから、テストだけクリアできるように情報を集めて、あとは自分たちでやっていました。
――現在はどのような生活をされていますか?例えば、休日はどのように過ごされていますか?
一つはパソコン組み立てです。組み立てると言っても、部品を組み合わせてプラモデルみたいなものです。自分で部品を買ってきて、半年に一回ぐらい作っています。他には、本読んだり、ウェブ小説を読んだりもしています。もう一つは、二週間に一回、大阪の施設に入っている親父のところにお見舞いにいきつつ、少し妻とドライブしてお茶をするということをやっています。他にも妻と1か月に1、2回ぐらい行きたいところに電車で行っています。日帰りで一番遠くまで行ったのは富山ですね。あとは数年一回、大きな旅行をします。去年の夏は山口と北九州の温泉に行きました。そういうので夫婦で楽しんでいます。
――先生の研究分野と具体的な研究内容を教えてください。
柱が二つあります。一つは、歴史的なアプローチで「自学主義」の系譜を研究しています。教師が教えて生徒が学ぶという構図ではなく、子どもが学ぶことを教師が支援する。デューイのいうコペルニクス的転回です。新教育が世界的に見て1920年代にピークを迎えますが、それを今の自発的学習の系譜の源流として捉え、どのような形で進んできたのかを大学院生のころは研究していました。一方で、日本の近世・近代の教育の中にすでに「自学」という発想があったのではないかということが、今の研究です。これについては、辻本雅史氏の「学びの復権」が有名で、最終結論については納得できないのですが、分析は面白い。アクティブ・ラーニングの裏返しで、結局、学ばせよう学ばせようとする雰囲気を作ってしまうと子どもは学ばなくなる。一方で、待っていても誰も教えてくれなければ自分で学ばなければならない。テキストがなければ、観察から学ばなければならない。教えないことによって、子どもは、正しいのかということについての不安を感じながらも、むしろ知りたい、知ろうとすることに対してハングリーになるわけです。「自分で」ということは、まさに自学なんです。自学を前提するのが、日本の近世・近代までの教育でした。そして、実はそれは今も日本人の学習観の奥底に流れているのです。もうひとつはカリキュラム・マネジメントです。これはコースの教員集団で実践研究に取り組んでいます。これまでの取り組みをある程度論文にまとめてきています。カリキュラム・マネジメントについての研究は個人でもできますが、実践研究なので、コースの教員などと協働で取り組んでいます。
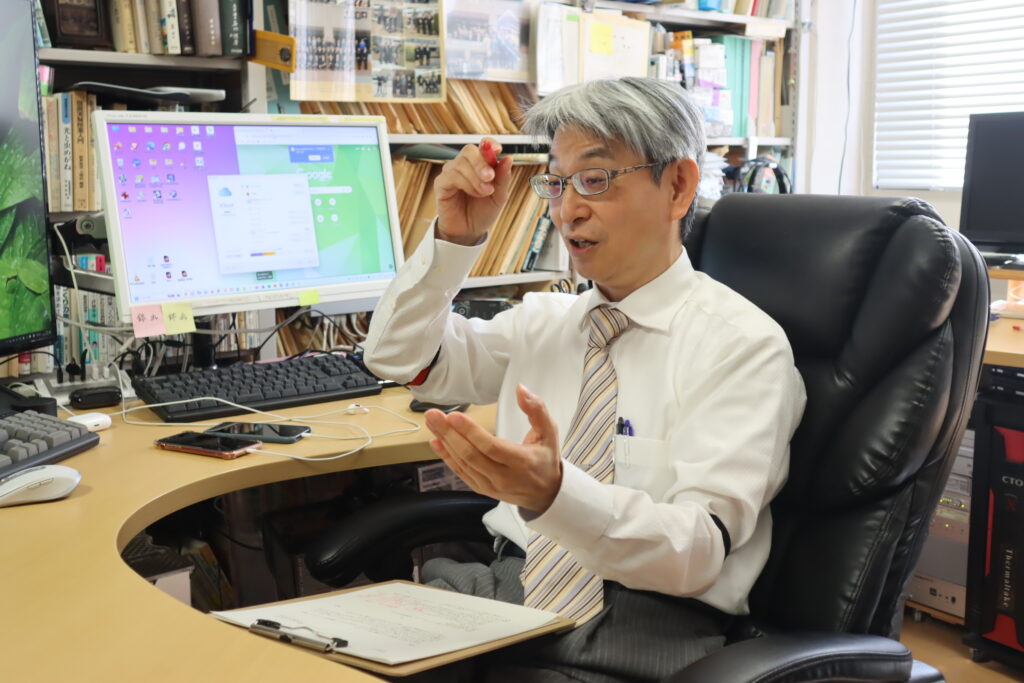
――先生のご専門や研究は学校や教育現場でどのように役立つものですか?
自学主義からだと、アクティブ・ラーニングですね。自律的や協働的(文科省的に言えば主体的や対話的)という点で、アクティブ・ラーニングにつながっていきます。以前は年間で3、4校に声をかけてもらい、講演をしたり研修会を組織したりしていました。一方でカリキュラム・マネジメントについては、2017~2020年度にかけて兵庫教育大附属中学校で、同校派遣の大学院のゼミ生と一緒にクロスカリキュラムの実践的研究を行いました。
――最後に、先生が考える本コースの魅力を教えてください。
実践を何かの裏付けとして視野に入れた研究、つまり実践研究が、まず特徴です。また総合的、統合的あるいは「通」教科的、教科が関連する、教科横断、他の教科をまたぐといった発想があります。魅力という意味では、非常に多種多様であることです。ある意味、極めることと、それと別の文脈として総合的にいろいろ目が配れるということは、教師には求められるので、そこが私たちのコースの魅力になると思います。
インタビュー実施:2023年11月8日
インタビュ―・写真:安齋律子、松田充
